傷を愛せるか
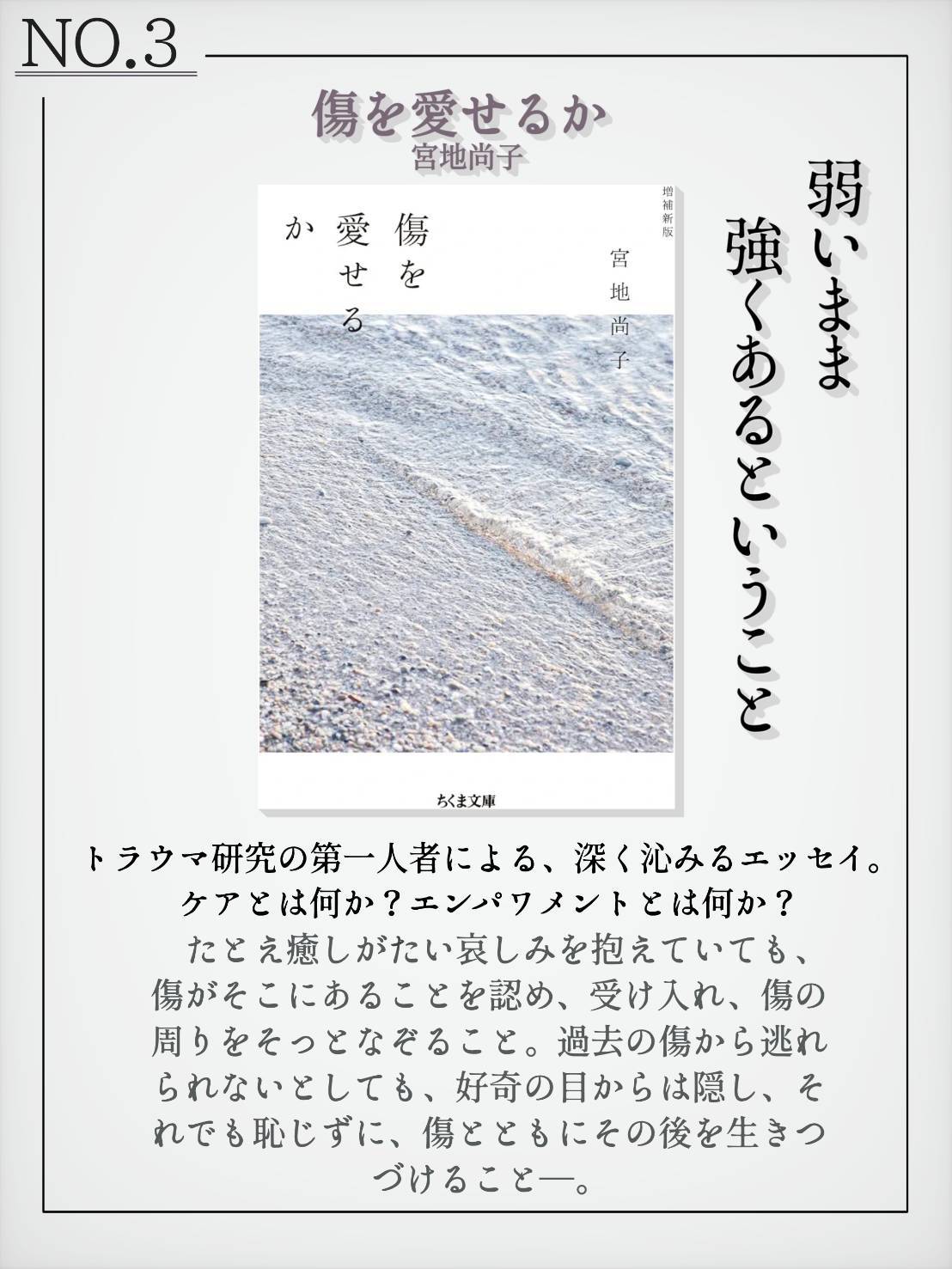
この歳になると、人間誰しもが傷のひとつやふたつを抱えながら生きているのだとしみじみ思う。そのことに気づいたのはわりと最近で、色々な人と関わるようになってからだった。
『傷を愛せるか』の著者宮地尚子は、トラウマ研究を行う学者であり精神科医でもある。彼女は文献や自分自身の経験を通して、傷との向きあい方を伝えている。
第一章 内なる海、内なる空にこんな一節がある。「なにもできなくても、見ていなければいけない」ではなく、「なにもできなくても、見ているだけでいい。なにもできなくても、そこにいるだけでいい」。
私たちは時々、傍観者にならざるを得ないときがある。当然当事者は苦しいけれど、ただ傍観者でいるしかないという無力感や恐怖、緊張は、はかり知れない。
私がうつ病だからだろうか。周りには深すぎる傷を負った人たちが集まってくる。その人たちから傷の話を聞くたびに、ああなんて無力なんだろうと思う。どんなに苦しくても、本人を救ってあげたくても、私には何もできない。
しかし、宮地尚子は言う。見守るという行為にはおおきな力が秘められていること。証人や目撃者になることは、被害者の救いになりえること。ずっと心に引っかかっていた透明な棘が、ひとつなくなった気がした。私は無力な傍観者ではなく、彼らが傷を負って、それでも幸せになっていく過程を見続ける証人であり、目撃者なのだと思えたから。
また宮地尚子は、著書の中で『包帯クラブ』という作品を引用しているが、その登場人物であるワラが印象深いことを言っている。
「何にもならないのはわかるよ。何にもならないことの証としてでも包帯を巻いていこうよ」。
この言葉には思わずハッとさせられる。自分の傷と向きあったとしても、その傷が必ずしも癒えるとは限らない。無意味かもしれない。救われないかもしれない。それでも、それを認めて、それごと自分のなかに残すことをワラは訴えている。確かにそうだと思う。どうあがいたって何も良くならなくても、治らなくても、苦しいままでも、ガッカリしたり落ち込むことはないんだ。そうか、と素直に思えた。
この本に出会う前からぼんやりと考えていたことがある。体は周期的に細胞が入れ替わるから、基本的には過去とは別人だ。しかし、一生ものの傷跡ならばずっと残り続ける。また、記憶や思い出も自分のこころにずっと残り続ける。つまり、私たちのこころと体に刻まれたもの=傷が私たちを私たちたらしめるんじゃないか。今回この本を読んで、もしも傷が私たちのアイデンティティとなりえて、不変であり、中核であるならば、『傷を愛せるか』とは自分を愛せるかとニアイコールなのかもしれない。
著書の最後に、宮地尚子は題名に対するアンサーのようなものを書いて締めくくっている。教会の窓から降りそそぐ一筋の光のような、やわらかな肯定の言葉だと思った。
私たちはどのように傷を愛すればいいのか、どのように傷と向きあえばいいのか、ぜひこの本を読んで自分自身で確かめてみてほしい。そして、あなた自身の傷を認めて、その傷ごとあなた自身を愛してみてほしい。
一応、私が利用している電子書籍載せます。購入はこちら
リピート購入の方、一応クーポンあります↓